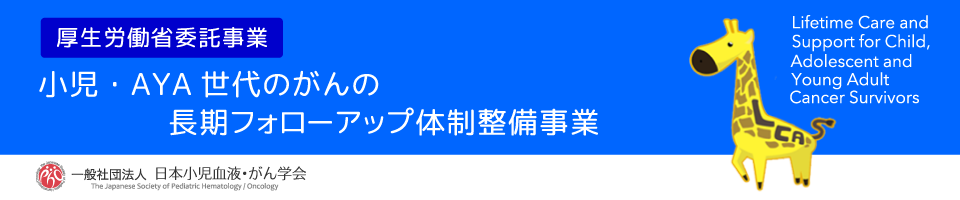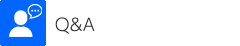はじめに
このQ&A集は、「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体制事業」が行う研修会(LCAS)の終了後に受講者に対して行ったアンケートに記載された質問に対し、研修会スタッフが手分けして回答を作成したもので、治療ガイドラインなどとは異なります。研修会のスケジュール上、十分な質疑応答の時間をお割けなかったことに対する補完の意味も含めて作成しております。受講者のみならず、小児がんの長期フォローに携わる様々な医療スタッフのお役にたてば幸いです。
Q&A
※質問内容をクリックすると回答が表示されます。
-
治療サマリーについて
| Q |
A 複数の施設で治療された症例に関しては、治療サマリーの作成に困難を感じることが多いと思います。特に治療後時間が経てば経つほど、担当医が交代したりして、正確な情報を得ることが困難になります。そのためにも、その患者さんのゲートキーパーになる施設においては、治療のたび毎に、その治療内容の正確な情報を治療施行施設から診療情報提供書として入手しておくことが重要になります。陽子線治療で専門施設にお願いしたとき、手術で専門施設に移動した場合などです。また紹介施設にとっては負担になりますが、転院時には治療サマリー(それまでの自院での治療内容のまとめ)を作成して、それを紹介状に添付して紹介することをお願いするのも、今後は有効かもしれません。以前中川原先生が病院電子カルテデータの抽出やどこでもMy病院のようなクラウドシステムを開発されていましたが、継続性と個人情報管理の敷居が高く、患者ごとのクラウド等利用した情報集約の予定は現在の所ありません。
|
||
|---|---|---|---|
| Q |
A ご指摘の通り、かなり以前に治療を受けた方や、再発、合併症等のためプロトコール通りでない治療を行われた患者さんでは、全ての薬剤について正確な投与量を把握することが困難な場合があります。こうした方に対しては、現在はpdf版のみの対応ですが、「短縮版」の治療のまとめがあります。短縮版では、晩期合併症の可能性がよく知られているアントラサイクリン系、プラチナ製剤、VP-16、アルキル化剤、延べ1年以上のステロイド投与に絞って、投与歴が「有」か「無」かを記入する形式となっていますので、短縮版治療のまとめをご活用いただければと思います。また通常版をご使用になる場合は、把握できる範囲での記載で結構かと思います。
|
||
-
フォローアップ手帳について
| Q |
A 分子標的薬や抗体製剤などは、歴史が浅いこともあって、一部の薬剤では長期的な影響が明らかになりつつありますが、多くは晩期合併症についての情報が少ないのが現状です。薬剤にもよりますが、投与歴の有無、連日投与する薬剤では投与期間、間欠的に投与する薬剤では投与回数などがわかるようになっていればよいのではないかと思います。
|
||
|---|---|---|---|
| Q |
A はい。FU手帳はENT時に「治療のまとめ」に記載(途中までで良い)してお渡しください。
その際「外来で行う治療の図表」という欄がありますので、併せてご利用いただくと、外来治療の進捗確認に役立ちます。 治療が終了する際に改めて「治療のまとめ」を追記載してください。毎回の受診ごとに「17.外来問診票&受診記録」に追記載を行い、手帳の必要性を患者さんご家族に啓発いたします。 記載される先生方には大変お手間をおかけします。患者さんアンケートより回答者の約4割に「治療開始後の早い時期に手帳は受け取りたい」という希望がありましたので、FU手帳をまめにつけることは長期フォローアップのモチベーション向上に役立つものと考えます。是非ご協力をお願いします |
||
| Q |
A FU手帳や治療サマリーにはmg/kg(またはmg/m2)で実際に投与された通り記載してください。最新版の治療サマリー(JCCG長期フォローアップ委員会作、ver4.3)では入力の際に単位をどちらでも選択できるようにしています。将来2次がんを発症した場合も、結局のところは疾患情報とその時のPSや主要臓器機能などを考慮して治療は選択されます。そのためにmg/kgをmg/m2に換算する必要はないと思います。
|
||
| Q |
A フォローアップ手帳は個々の施設で作成し使用している場合もありますが、JCCGの長期フォローアップ委員会が作成し、LCASでも一例として使用している手帳は、昨年度は、小児がん拠点病院の各地域ブロックの代表7施設に配布し、そこから連携病院へ配布をしていただきました。今年度は、患者会からの要望も大きいので、全国患者会ネットワークに参加している43団体で配布を希望しているところ、昨年度のような小児がん拠点病院を介しての配布、またLCAS参加施設で要望があった施設への配布などを考えています。昨年からはハートリンクから資金援助をしていただいています。
|
||
-
認知機能について
| Q |
A 視覚障害のある子どもの発達診断では、感情・意思・思考・言語・認知・社会性など様々な領域への影響を推測しながら評価することが望まれます。一般標準化された認知機能検査は、視覚を介して実施される検査項目が含まれるため、盲児には適用できません。このため、既存の認知機能・知能検査を実施可能部分に限って実施したり、課題提示の内容や回答方法を改変して実施するなど、得られたデータから推定した評価が行われています。改変した検査の解釈のためには、本来の認知機能検査のねらいと評価基準を理解している必要があり、熟練した専門家が実施しなければなりません。また、保護者評価による発達診断テストも参考とされますが、解釈については、視覚障害の程度や生活状況をあわせて慎重に行う必要があります。発達支援においては、生活状況の観察や、発達支援を行いながらの、認知の特徴の把握が欠かせません。これにより、検査では把握できない実体把握が可能となります。
盲学校では、入学時に、視覚機能について医療機関の診断を取っています。入学時に視力があっても進行性の病気をもつ子どもは盲学校で教育を受ける場合があり、疾患の管理や義眼の装着など医療機関との連携が必要となることがあります。盲児には、定型発達の重要な時期に「発達の壁」があり、そこでつまずくと、発達の遅延をより長くしたり、自己刺激的な行動が出てきたりします。この壁を超える適切な療育・教育、指導が重要ですので、早期に支援の必要性を判断し、連携した支援を始めることが求められます。 例えば、網膜芽細胞腫の長期フォローアップでは、診断時(乳幼児期)から長期に亘り、診察していますので、視覚障害のある場合、眼科医や小児科医が診て発達の遅れの有無と発達検査の必要性、患児がもつ力をどのように伸ばすのがよいかなどをその時々に評価し、提案をしています。両側性網膜芽細胞腫では、認知発達の遅れがみられることがあります。網膜芽細胞腫を理解している臨床心理士が発達検査を実施し、発達の遅れがあると診断されれば、1歳6か月、2歳、それ以降は就学前まで年1回、定期的に発達評価を行います。評価には、広D-K式視覚障害児用発達診断検査や新版K式発達検査が用いられています。時に、網膜芽細胞腫で重度の発達遅滞を認める場合には、13q- 症候群などの染色体異常がある可能性がありますので、臨床遺伝専門医が遺伝相談の中で対応します。 視覚障害を生じるがんの種類により、対応は異なりますので、専門医、視能訓練士、臨床心理士、看護師、療育や特別支援学校の教員などが連携した支援が重要です。 |
||
|---|---|---|---|
| Q |
A 化学療法後には、注意欠陥障害、処理速度低下、複数同時作業力低下、巧緻運動障害、高次脳機能障害という一連の神経障害をきたす場合があることが知られており、ケモブレインまたは化学療法関連認知障害(Chemotherapy-related cognitive impairment (CRCI))と呼ばれ、成人および小児の、特にメソトレキセート(MTX)を使用するレジメンでの発症がよく知られています。小児領域ではケモブレインという用語はほとんど使用されていないと思いますが、小児では放射線治療を併用する場合が多く、放射線治療後の認知機能障害がより重篤なこと、発達途上の小児ではそもそも神経心理や社会生活は年齢とともに変化し、治療前との比較というより成長発達への影響という意味でとらえられてきたこと、成人領域では晩期合併症を問題視し始めたのは比較的最近でケモブレインという用語が治療前との変化という意味で使用されてきたこと等が理由ではないかと思われます。MTXによる認知機能障害の機序ですが、MTXがミクログリアを活性化させ希突起膠細胞系列のダイナミクスや星細胞の再活性化を障害することが報告されており、これらが長期的な認知機能障害につながるのではないかと考えられています。
|
||
-
二次がんについて
| Q |
A 小児がん経験者では、これまでに多数のコホート研究が報告され、治療後 20 年間の二次がん累積発症リスクは 2~5%で、これは一般集団で推定される値よりも標準化罹患比(SIR)で 3~20 倍高いといわれています。AYAがん患者の二次がん研究はまだ多くはありませんが、最近報告された研究(Bright, CJ et al: Lancet Oncology, 2019)では診断後35年で12-26%(原疾患によって異なる)とされ、小児がん経験者よりも高いくらいですが、一般集団のがん罹患が多いのでSIRは1.3-2.0程度です。
小児がんやAYAがんで二次がんのリスクが高くなる理由としては、遺伝的な要因が一部存在すること(Li-Fraumeni症候群など)、発育盛りの時期に発病・治療をすること、治療終了後の生命予後が長いため潜伏期の長い合併症が検出されやすいなどが考えられます。 |
||
|---|---|---|---|
| Q |
A ご指摘のように、そもそも甲状腺の超音波検査を行うと、一般集団においてどの程度の頻度で異常が見つかるのかというエビデンスが少なく、異常所見が見つかり不安になると言うことはあると思います。
小児がん長期フォローアップガイドラインハーモナイゼーションの結果(Clement, SC et al: Cancer Treat Rev 63:28–39,2018)では以下のように書かれています。 ・甲状腺への放射線照射もしくは131I-MIBG 治療を受けた経験者は二次性甲状腺がんのリスクを持つ ・ 症状があるなしにかかわらず、甲状腺腫瘤が見られたら医療機関に相談する ・ 甲状腺への放射線照射を受けた経験者は、二次性甲状腺がんのスクリーニング方法の長所・短所を注意深く考慮した後に、サーベイランスの方法を決定する ・ サーベイランスは、甲状腺の触診と超音波検査とどちらかのスクリーニングが推奨される。2つの方法の長所・短所を説明し、経験者の希望を考慮する。良性か悪性かを決めるのに侵襲的な手技を必要とすることがあり得ることを説明しておく。異常が認められなかった時には、触診の場合には1–2 年毎、超音波検査の場合には3–5年毎のフォローアップが推奨される ・ 甲状腺がんの治療に熟練した施設では、適切な放射線読影や臨床的なリスクの評価で不必要な侵襲的な手技を少なくするために、超音波検査と針生検が推奨される ・ 定期的なサーベイランスをしない場合においても、医学的なフォローアップ時には甲状腺の触診を推奨する ・ 何らかの甲状腺腫瘤が認められたら、甲状腺専門医にコンサルすることが推奨される |
||
-
放射線治療について
| Q |
A COG のフォローアップガイドラインは、晩期有害事象のスクリーニングやマネージメントを行うために、リスクの高い群を効果的に抽出するためのツールです。従いましてAgentやrisk factor として挙げられているものが、その有害事象の原因であると帰結するべきではありません。COGのガイドラインの甲状腺がんのAgentにリストアップされているような頭蓋照射、ワルダイヤーの照射は甲状腺がんの誘因とはなり得ません。しかし頭蓋照射を行った患者が頸部の照射の既往があったり、神経芽腫の患者であったりする可能性がありますので、スクリーニングにおいて、着目すべき点にはなります。
一方、全中枢神経照射では、脊髄を真後ろから、照射することが多いため、脊髄の前方にある甲状腺が照射されることになり、このため甲状腺がんの頻度が増加すると考えられています。散乱線によるものかという、質問に対する回答は控えさせていただきます。画像診断では散乱線という表現が使われますが、放射線治療では散乱線による現象と、そうでない放射線を区別して議論することはできません。「リスクを取る」という表現については、慎重に考えていた方が良いと思います。大辞林によると、「リスクを取る」とは、あえて危険に挑む、という意味のようです。標準治療を、あえて危険に挑むという認識を持たせるのは、治療やその後の有害事象や、経過観察の意義について、誤った認識を持たせることになります。 |
||
|---|---|---|---|
-
生殖機能(妊孕性:にんようせい)について
| Q |
A 卵巣組織凍結に関してですが、がん治療まで時間的余裕が無い場合、初潮開始まえの小児がん患者などがその適応として考えられています。なお、日本産科婦人科学会によって認定された施設でのみ対応が可能となっております。ランダムスタート法でも2週間は要してしまいますが、最近では生理周期に関わらず卵巣刺激を行うランダムスタート調節卵巣刺激が導入されつつあり、治療開始までの時間を有効に利用できるようになりました。「生理周期とずれて3週間くらいかかり」に対しますコメントとなります。
|
||
|---|---|---|---|
| Q |
A 海外からの報告では、非ホジキンリンパ腫もあげられています。原則として、卵巣に腫瘍細胞が存在すると考えられる疾患や進行状態がMRDとして問題となります。
|
||
| Q |
A 卵子凍結を行う場合、一般的には月経周期に則った形で採卵を行います。例えば、月経3日目から卵胞刺激ホルモンの注射を開始し、卵胞が約2cmになるまで2-4日おきの採血・超音波モニタリングのもと、連日注射を行います(調節卵巣刺激)。通常は卵胞が育つまで10~14日程度かかり、卵胞が育った時点で採卵を決定します。なお、調節卵巣刺激には内服薬を用いる方法がありますが、発育する卵胞数が多いとはいえないので、注射を用いた刺激方法が選択されることが多いと思います。また、近年は月経周期に則らないで調節卵巣刺激を行う方法も開発されております(ランダムスタート法)。
|
||
| Q |
A 卵巣組織凍結を行う場合、基本的には(回答者施設では)手術前日に入院していただき、手術は一時間程度で終了します。その後、手術翌日(場合によっては当日)から食事を開始し、術後二日目に退院としています。なお、手術を行うためにはインフォームド・アセントが必要だと考えておりますので、妊孕性温存の説明を別日に行う必要性があります。
|
||
| Q |
A 数日で帰っていかれます。数日で帰って行かれる状態の患者さんのみが適応となります。状況によっては、前日あるいは当日のラボデータや状態によって、卵巣組織凍結をキャンセルせざるを得ないケースもあります。がん治療医と妊孕性温存治療医との密な連携が必要となります。
|
||
| Q |
A 生産率については、文献的な報告をもとにしてお話ししており、特にDonnezらのレビューから情報提供しております(Donnez, New England Journal of Medicine, 2017 PMID 29069558)。その文献では妊娠率は29-42%で生産率(流産を考慮したもの)は23-36%となっております。ただし、これらは検討症例数も多くないことから、今後変化する可能性は十分にあることも付け加えてお話ししております。また、妊娠の方法については体外受精を選択せざるを得ない場合もございますが、体外受精に関しても極めて詳細ではないもののお話しさせていただいております。
|
||
| Q |
A どのように受けていくのか、ということについては、それまでの経験や親や医療者を含めた周囲の関わりにより、個々にかなり差が生じるのではないかと思います。またその個人にとっても、その時大切にしているものや関心事はその方のライフイベントやまた周囲との関係性などで変化もします。実際に、思春期の経験者がその時期には、不妊の可能性であることにについて「自分は別に子どもいらないので大丈夫」と言っていたとしても、彼氏ができたり、それが結婚などを考える関係になると、不妊の可能性のことが気になり、それについて相談してくる場合などもあります。経験者がそのようなことを体験したり感じたりしうることを予測しながら、長期フォローアップの中で、体験者の感覚を捉えることが大切かと思います。
また、過去の説明の程度がはっきりしない経験者が外来に来た際に、その時の経験者にとって不妊の可能性を聞くことが与える影響が大きい場合などもあるので、成人だからといって不妊の可能性について一方的に説明するなどすることがないように、看護師、心理士など多職種で計画的な関わりをすることが望ましいかと思います。質問の主旨とは少し異なるかもしれません。 |
||
| Q |
A こういう場合、子ども自身の闘病や入院の記憶が曖昧、または欠落していることが予想されます。伝えるべき最も大切なことは「なぜこれまで定期通院が必要だったのか」「なぜこれからも定期通院が必要なのか」です。それを伝え理解してもらうためにはおのずと病名や合併症の説明が必要になります。まずは定期的に通院する当の子どもがどこまで記憶していて今どう感じているかが大切です。
「どうしてまた来年も病院に来ないといけないの?」と感じているならその時が好機でしょう。子どもから疑問の発信がない場合は進級や進学を契機に定期通院に関する思いを聴き、いつ、誰から、どう話すか家族と相談するのがお薦めです。それには折に触れて普段の子どもの様子や発言を気に留めておくことが大切だと思います。看護師や心理士、保育士、CLSなどから子どもや親の情報を得て相談することも良いでしょう。 臓器特異的な合併症の説明は、検査や治療が必要な時、あるいは生活に影響が出る可能性がある時などが好機になり得ます。低身長なら負荷試験を行う時、妊孕性なら学校の保健の授業で性について習う時またはTanner Stageの評価をする時、手術痕なら水泳の授業が始まる前、などはいかがでしょうか。 これらには正解も間違いもありません。病気や体のこと以外も普段から率直に話し合える関係性の構築を心掛け、多職種で協働して子どもと家族を理解し情報共有していることが大切です。 |
||
| Q |
A 妊孕性温存に必要な処置をすることも、抗がん剤の治療を開始することも、本人の納得の上に行うことが、基本となります。病気を告知することが不安な親の気持ちを聴きとりつつ、親を励ましサポートをしながら、病気の説明、治療や治療の影響の説明、妊孕性温存のための処置の説明を併せて行いましょう。妊孕性温存のための処置の説明は、産婦人科や泌尿器科の医師と連携して行います。子どもがよく理解できるように、子どもの発達に合わせて絵などを用いながら、最大限の工夫をして説明をします。しかし「妊孕性」を実感をもって理解することは、思春期の子どもであっても難しいかも知れません。それでも、医師がきちんと説明すること、また、父や母(親権者)はどう考えているのかをきちんと伝えていくことが大切です。
|
||
| Q |
A 採血によるホルモン検査の値など合わせて総合的な判断で、定期的な月経、なおかつ女性ホルモンの正常値が継続していれば、早期に婦人科受診を進める必要はないかと思います。思春期以降の患者で、治療の合併症から、妊孕性についてあらかじめリスクが高いことがわかっている場合、今後の移行の時期も考慮して、早期に婦人科受診を進めること(紹介)はよいかと思います。移植など治療内容によっては、治療中から婦人科との連携を図っている施設もあります。
|
||
-
成人科の先生への質問
| Q |
A 治療科の医師は、専門の領域の有害事象に注意は注ぎますが、他領域にはなかなか注意が回らないのが実状です。看護師さんはフラットな目で患者と接する事ができるので、脳腫瘍患者であれば循環器領域や内分泌領域(甲状腺や副腎)への関心を示して頂きたいと思います。特に、この2領域は全身倦怠感や注意力の低下等が最初の症状であることが多く、この愁訴は医師に面と向かっては言いにくい事柄でもあります。簡単な声かけでも良いのでお願い申しあげます。
また、学業不振や職場での不具合(上司・同僚との関係が上手に構築できない)などの相談を気軽に出来る様に外来で務めて頂きたいと思います。長期追跡患者は半年に1回、1年に1回程度の外来受診となろうかと思います。滅多にない外来ですので、むしろ3週回しの化学療法患者より、患者サイドは話したいことが多くあると思います。是非、お話しを聞き出して頂きたいと思います。そのためにはとにかく顔見知りになっておくことです。私は長期追跡を阻害している大きな要因は患者・家族への継続的な接触が円滑にできないことだと感じております。医師の転勤(主治医の交代)はその最たるものですが、外来看護師の短期間での部門変更もその要因と考えてよいかもしれません。マンネリはダメですが、毎年新しい看護師さんというのでは、信頼関係は構築できません。病院管理者にも是非注意喚起をしたいところです。 |
||
|---|---|---|---|
| < | 1 | 2 | 3 | > |